秋のアウトドアで気をつけたい「マダニ」

夏が終わり秋になれば愛犬達が楽しく遊べる気温になり、アウトドアへ愛犬を連れて出掛けることが多くなる人も多いと思う。
ただ、そんな楽しさの陰には恐ろしい吸血生物が潜んでいる…それがマダニ。
マダニはクモの仲間に分類される「吸血性ダニ」で、人や犬の皮膚にかみつき、数日かけてじっくりと血を吸う。
マダニはウイルスや細菌を体に持っていて、血を吸っている時に人や犬にうつすことがある。
マダニ感染症って呼ばれる病気になってしまうことがあるんだ。
この感染症は危険なものが多く、マダニ感染症を100%防ぐ方法は無いから、感染しないための対策をしっかりと立てておく事が重要になる。
という事でマダニ感染症について記事を書いてみたので、よかったら最後まで読んで、愛犬のマダニ感染症対策に役立ててほしい。
ノミ・ダニ駆除薬では完全に防ぎきれない

防ぎきれない理由は以下の通り。
- フィラリア予防薬と一体化している経口薬は、一旦マダニに噛まれて血を吸われてからしか効果がない。
マダニが吸った愛犬の血の中にある殺虫成分でマダニを駆除する。
つまり、いったん噛まれて血を吸われている間に、マダニ感染症に感染する可能性があるんだ。 - スポットタイプは薬剤が愛犬の皮脂にくっついて、噛まれる前に駆除できる設計で作られている。
が、雨や水遊び等で皮脂(薬剤)が流れてしまって効果が無くなっている部分ができたりする可能性がある。
特に足の裏などが要注意ポイント。
愛犬におすすめのマダニ対策(+猫飼いさんは要注意)

経口タイプやスポットタイプのノミダニ駆除薬で対策をした上でさらに下記の対策も検討してほしい。
- 足の下の方まである服を着せてマダニがくっつかにように防御。
- 犬用のダニ避けスプレーを草木の多いところで遊ばせる直前にかける。
(※犬用のダニよけスプレーには、猫にとって危険な成分(ピレスロイド系や一部の精油)が含まれていることがある。犬と猫を一緒に飼っているご家庭では、犬用スプレーを使った直後に猫が舐めてしまうと中毒のリスクがあるため注意が必要。) - 家に帰ってきたら、ブラッシングをしながらマダニがくっついていないかチェック。
マダニは犬の体ならどこにでも付く可能性があるが、特に「耳・目・口まわり」「首輪の下」「わきの下や内股」「お腹」「しっぽの付け根」など、毛が薄くて血管が通っている場所を好む。散歩や草むら遊びの後は、こうした部位を重点的にチェックすると、早期発見につながる。
愛犬はマダニに噛まれても痒くも痛くも無いので噛まれている事に気付かない

マダニはとても優秀な吸血ダニなんだ。
噛みつくときには痛みを感じさせない“麻酔成分”を、血を吸っている間には“血が固まらない成分”や“かゆみを抑える成分”を出している。
そのため、犬はマダニに噛まれてもほとんど気付かない。
だからこそ、飼主が手で触って、目で確かめるチェックをすることが欠かせないんだ。
マダニを見ても絶対にやってはいけない事

愛犬や自分にマダニがくっついていても絶対に潰してはいけない。
先にも書いたんだけど、マダニは様々な菌やウイルスの媒介者だから、潰してしまうと、その菌やウイルスが飛び出てきてしまい感染してしまうリスクがあるんだ。
じゃあ引っこ抜けばいいじゃない!と思うかもしれないんだけど、それがうまくいかない事が多いんだ。
マダニは口にノコギリのようなトゲがついた“かぎ爪”を持っていて、皮膚に突き刺すと自分の唾液でセメントのように固めて固定するんだ。そのため、無理に引っ張ると頭(口の部分)だけが皮膚に残ってしまい、体だけがちぎれることがあるんだ。残った口は炎症や感染の原因になるから、自己処理は危険。
基本的には犬は動物病院で、人は人間の病院で確実に取ってもらった方が安全。
自己流で取り除こうとせず、必ず皮膚科など医療機関で処置を受けて欲しい。
マダニが媒介する感染症リスト

代表的なマダニ感染症。
上でも書いたけど、マダニに噛まれたら病院で取り除いてもらうのが基本。
そして、噛まれた後に愛犬の体調が悪そうなら動物病院へ。人なら病院へ必ずいく事!
人がかかる主なマダニ感染症
-
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)
・ウイルス性の感染症で、西日本を中心に報告多数
・発熱、嘔吐、下痢、血小板減少 → 重症化すると致死率高い
・犬や猫を介して人に感染することもある -
日本紅斑熱
・リケッチアという細菌が原因
・高熱・全身の発疹・刺し口が特徴
・抗生物質で治療可能だが、放置すると危険 -
ライム病
・ボレリアという細菌が原因
・赤い輪っか状の発疹(遊走性紅斑)、発熱、関節炎、神経症状
・長期化すると後遺症のリスクあり
・抗生物質が有効。初期に治療すれば治りやすいけど、遅れると関節炎や神経症状など慢性化・後遺症が残るリスクあり。 -
野兎病
・フランシセラ菌が原因
・発熱、リンパ節腫脹、化膿
・国内でも北海道や本州で発生歴あり
・発見が遅れると重症化するが、適切な抗生物質を早期投与すれば治癒率は高い。 -
ダニ媒介性脳炎(TBE)
・ヨーロッパやロシア、中国で有名な脳炎ウイルス
・神経症状や後遺症のリスク
・日本でも北海道で確認例あり
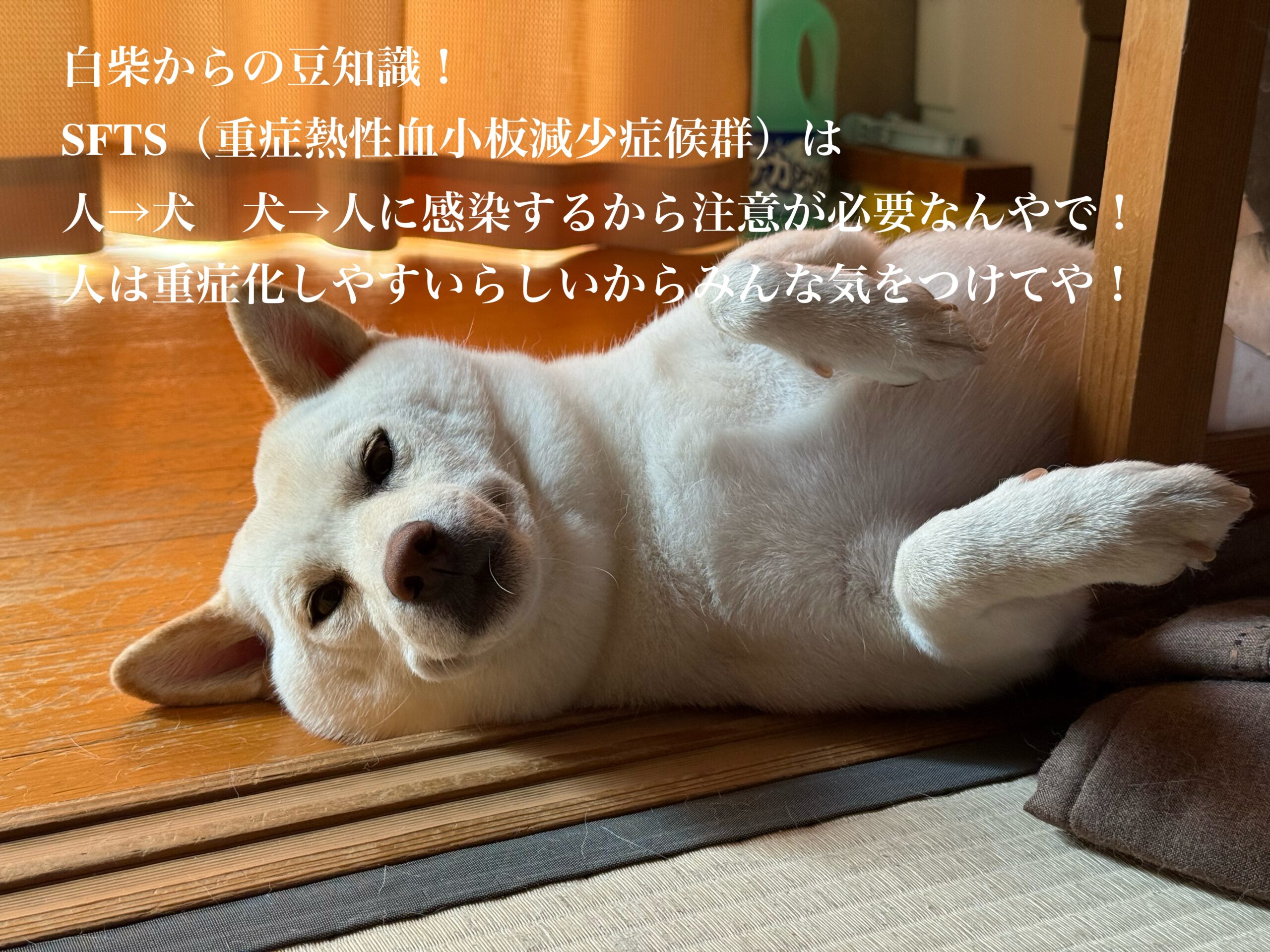
犬がかかる主なマダニ感染症
-
ライム病
・発熱、関節炎、足を引きずる、元気消失など
・抗生物質が有効。初期に治療すれば治りやすいけど、遅れると関節炎や神経症状など慢性化・後遺症が残るリスクあり。 -
エーリキア症
・発熱、貧血、食欲不振
・重症化すると命に関わる
・抗生物質で治療が可能 -
バベシア症
・発熱、貧血、食欲不振
・重症化すると命に関わる
・原虫(寄生虫の一種)が原因。抗原虫薬や輸血など、より重い治療が必要になることがある。
-
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)
・犬も感染する可能性あり
・さらに飼い主に二次感染させるリスクがあるとされるマダニ感染症は「早期に病院に行けば大丈夫」とは言い切れない。日本紅斑熱やライム病のように抗生物質が効く感染症なら、初期に受診すれば回復できる可能性は高い。しかし、SFTSやダニ媒介性脳炎のようなウイルス性の感染症の特効薬がない病気もあり、その場合は早く病院に行っても重症化してしまうリスクがある。だからこそ、「噛まれない予防」と「噛まれたらすぐ受診」の両方が大切。
最後に
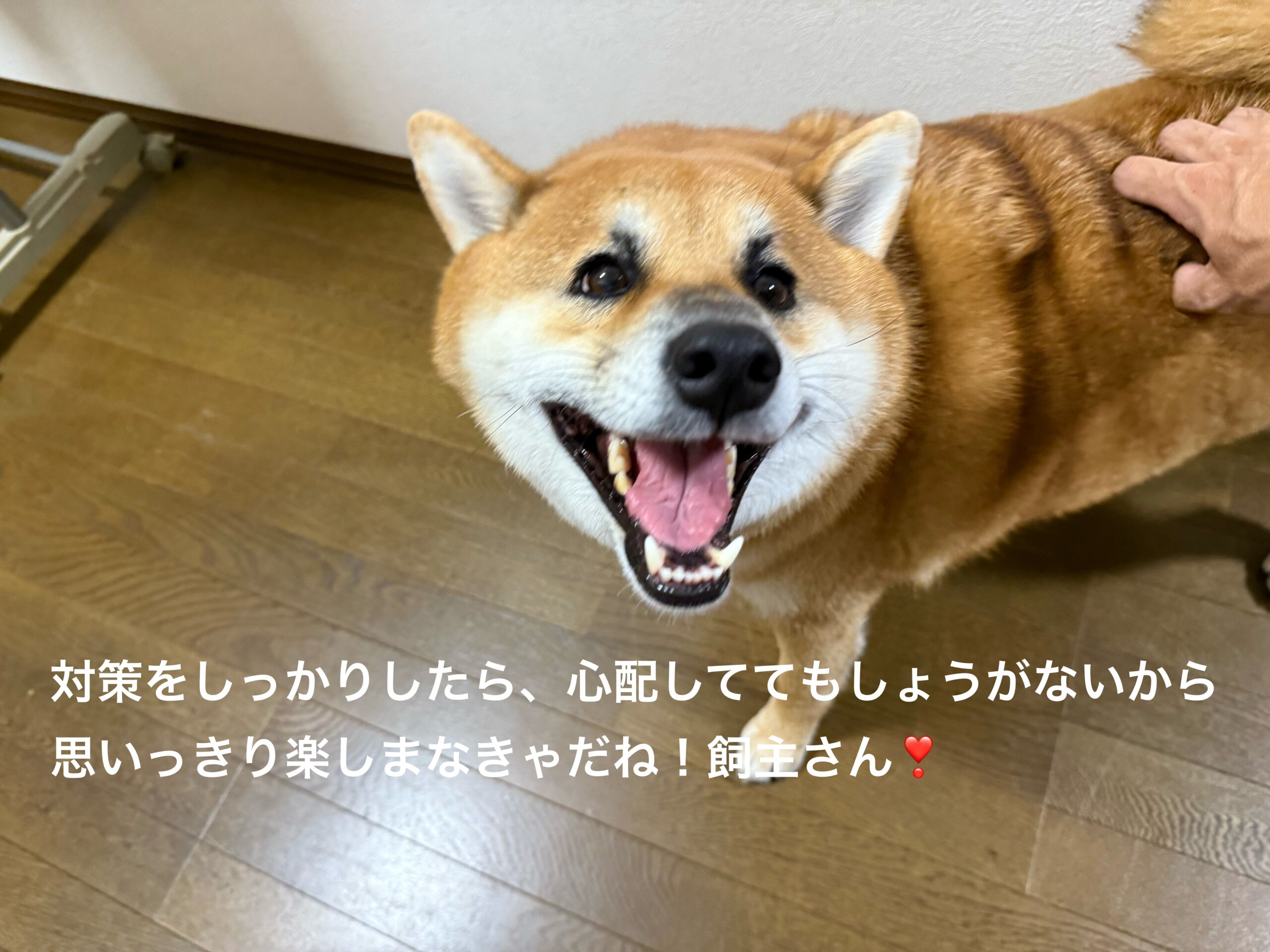
オレは今までマダニに刺された事は無いし、愛犬が刺された事も無い。
でも、オレは油断せずにウチの柴犬達は散歩から帰ってくるとブラッシングをしながらチェックしている。
今までないからと言って油断していると痛い目を見るという事を最近よく学ぶ。
だから世間で注意喚起をしてくている事に耳を傾けて対策をしていくという事が重要だと思う。
ちなみに、マダニは草の上で前足を広げて“待ち伏せ”して、通りかかった犬や人にしがみついてくるらしい。
これって考えるとかなり怖いよね!
