昭和の犬のしつけといえば・・・

昭和の犬のしつけといえば――。
オレは昭和53年生まれのバリバリ昭和っ子。
初めて犬の世話を任されたのは、中学に上がる頃だった。
当時の主流は「殿様と家来」。
飼主が絶対で、犬は従わせるもの。しかもその方法は暴力的で威圧的なやり方だった。
オレもそのやり方を真似してみたけど…結果は秒でアウト。
犬に嫌われ、近づけば噛まれそうな勢いで唸られるようになった。

近所のおじさんからは、
「完全に舐められてるぞ」
「服従しなければエサをあげちゃダメだ」
なんてアドバイスを受けた。
いまの愛犬家が聞いたら白目むくような話だけど、当時はそれが“常識”だったんだ。
そしてその名残は、現代でもちらほら見かける。
なぜ、科学的に間違ったしつけ方法が長い間“正しい”と信じられてきたのか。
この記事では、その背景と、いまも誤解されやすい犬の習性について解説していく。
上下関係神話の元ネタになった「誤解されたオオカミ研究」と「アルファ神話」
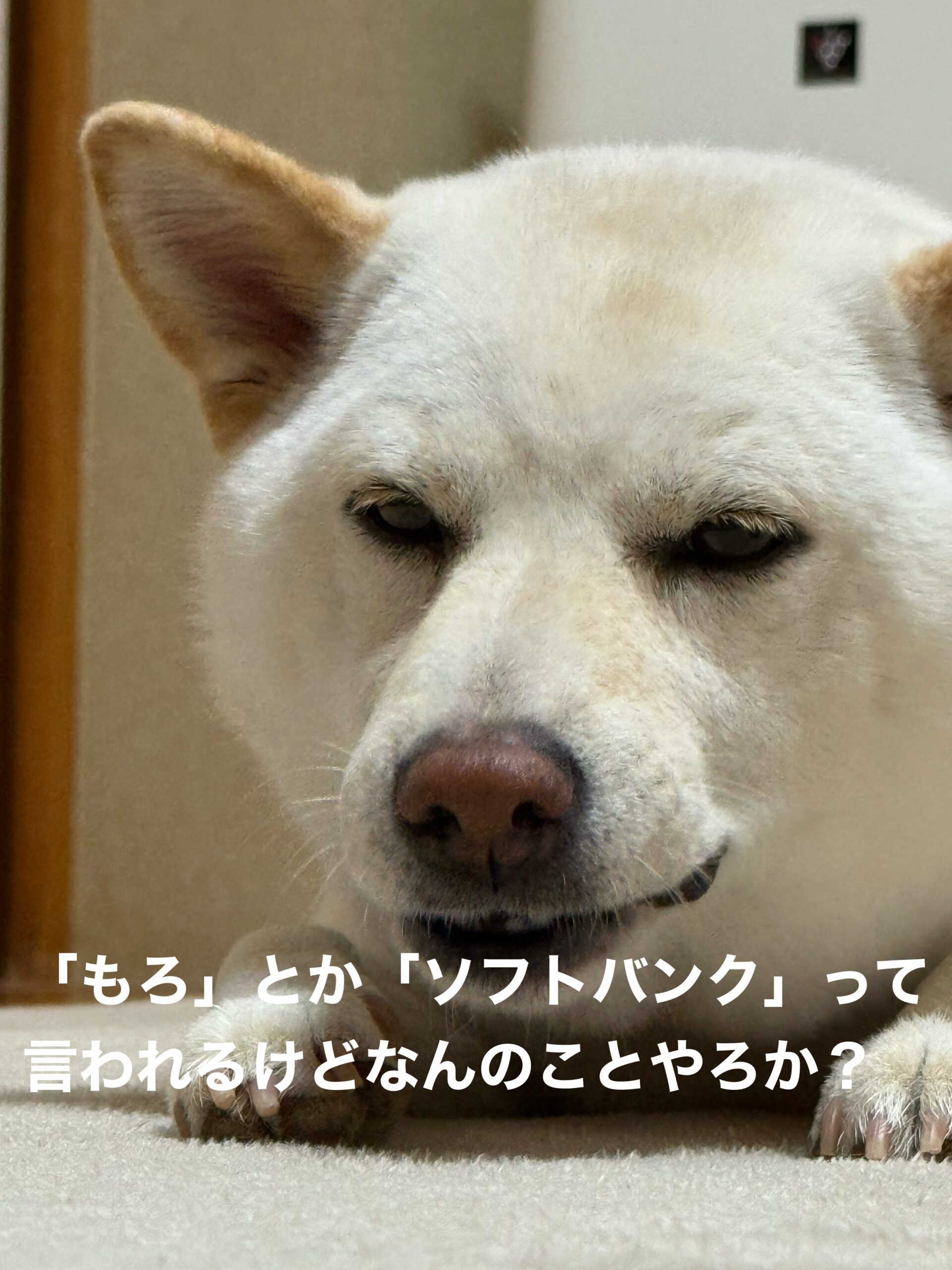
元ネタの研究
犬の「上下関係神話」のルーツは、1940〜1960年代にスイスの動物学者 ルドルフ・シェンクル(Rudolf Schenkel) が行ったオオカミ研究なんだ。
- 動物園の檻に入れられたオオカミの群れを観察して、
「アルファオス」「アルファメス」という支配的存在が群れを統率しているように見える
と報告した。 - この結果が「犬にも上下関係がある」という考えの原点になった。
その後1970〜1990年代にかけて、
「アルファシンドローム」
「犬は群れのリーダーに服従させるべき」
という考えがアメリカやヨーロッパのしつけ本や訓練士を通じて一気に広まった。
でも2000年代以降、デイヴィッド・メッチ(David Mech) らのフィールド研究で、事実は違うことが判明した。
- 野生のオオカミは「家族単位」で暮らしており、支配関係ではなく親子関係がベース。
- 「アルファ」という言葉は誤解を生むため、研究者自身が使用をやめた。
- 犬の行動学でも「上下関係ではなく、学習・経験・感情で行動する」と説明されるようになった。

間違った研究が昭和のしつけに与えた影響
この「オオカミの群れにはリーダーがいて他は従う」というイメージは、日本の 会社・軍隊・家庭の封建的文化 にピッタリはまった。
結果として、
- 「犬を叩いてでも服従させろ」
- 「飼い主が絶対的なボス」
みたいな昭和的しつけ文化が当たり前のように広がってしまったんだ。
でも実際の犬は、上下関係で動く動物じゃなくて、信頼と安心で動く動物。
恐怖や痛みによるしつけは、短期的に動きを止めても長期的には
- 飼い主への不信感
- 攻撃性や防衛行動の強化
につながる。
だから、オレが中学生の頃に飼っていた犬からメチャクチャ嫌われたのも、いま考えると当然。

今でも信じている人がいる間違った犬の迷信14選
うした誤解は、いまも形を変えて残っていて、「犬の常識」として語られていることが多い。
でも実はその多くが迷信レベルで、科学的にはまったく根拠がないんだ。
代表的なものをいくつか挙げてみる。
昭和時代の「しつけあるある!」と思って、ぜひ読んで欲しい。
もし、過去の間違った「いにしえのしつけ方法」を信じている人は、こそっと考えを改める機会にしてもらえればと思います。
1. 「トイレを失敗したら鼻を押し付ける」
実は犬は「なぜ押し付けられてるのか」が理解できない。トイレ嫌い・飼い主不信につながる。
2.「叩いてしつければ言うことを聞く」
暴力は恐怖で一時的に動きを止めるだけ。信頼関係が壊れて問題行動が悪化する。

3.「犬は上下関係で支配しないといけない」
最新の動物行動学では“リーダー=支配する存在”ではなく“リーダー=安心できる存在”になることが大切とされている。
4. 「オス犬は必ずマウンティングして支配を示す」
マウンティングは支配行動だけじゃなく、遊び・ストレス発散・興奮のサインでもある。
5. 「犬がしっぽを振っていたら全部うれしい」
実際は緊張・不安・警戒のしるしのことも多い。振り方や体全体の動きとセットで見る必要あり
6. 「犬は悪いことをしたらすぐに反省してる」
反省顔に見えるのは“飼い主の怒りを察して服従のサインを出しているだけ”。罪悪感じゃない。

7. 「犬を甘やかすとわがままになる」
愛情=甘やかしじゃない。むしろ安心できる環境があると学習がスムーズに進む。
8. 「犬は飼い主より先に食べてはいけない」
“上下関係”を誤解したしつけ。食事の順番で犬の支配性は変わらない。
9. 「飼い主が先にドアを出ないと犬にナメられる」
犬はただ「早く行きたい!」だけ。順番でリーダーは決まらない。
10.「犬がソファやベッドに上がると飼い主を下に見ている」
上下関係ではなく「心地いい場所が好き」なだけ。
11.「犬が前を歩くとリーダーシップを取られている」
散歩で先に行くのは「外が楽しいから」であって支配ではない。

12.「犬がお腹を見せるのは完全服従」
実際は「遊んで!」「なでて!」の甘えサインのことも多い。
13.「犬が吠えたらすぐに叱らないといけない」
吠えの理由は警戒や不安。叱るより原因を取り除く方が大事。
14.「犬は群れのボスに従う習性があるから飼い主は絶対的リーダーにならなければならない」
最新の行動学では「犬は人と協力関係を築く動物」とされ、狼のボス理論は完全否定されて
振り返ると、オレ自身もこの「いにしえのしつけ方法」を信じきって、犬に接してきたひとり。
でも人生の折り返しを迎え、今の白柴と赤柴を育てる中で気づいたのは、
「上下関係」や「支配」じゃなくて、「信頼」と「安心」で成り立つ関係こそが本物だということ。
オレの愛犬達は飼主との上下関係をできるだけ無くすよう育てた

オレも迷信を信じきって、過去にはリーダーウォーク・アイコンタクト・トリックを多数教え、寝食別で暮らす事が犬と人との幸せな形だと信じて実行してきた。
離婚を経験し、人生の折り返し地点を超えた。
今いる白柴と赤柴がオレの人生最後の犬だと思って育てるにあたって決めた事が、オレの子供と思って育てるという事。
リーダーウォークやアイコンタクトを強制せず、トリックも教えず、一緒に寝て、一緒にご飯を食べる。
とにかく話しかけ、とにかく頭や体をナデナデ❣️させてもらい、口癖は「いい子❣️」と「お利口さん❣️」。
叱る時は、何で叱られているか犬のわかるタイミングだけ合わせて短く叱る。

結果、白柴と赤柴は「お手」と「おすわり」と「ふせ」しか知らないこいつらは、実に個性的で、実にユニークなかわいい柴犬に育った。
オレのことを気遣って、思い遣ってくれる子に育った。
そんなオレは完全な犬バカ変態アラフィフおじさんに変身した。
結局、犬との関係は“上下関係”じゃなくて、“信頼と安心”なんだと思う。
昭和の迷信に縛られなくても、愛犬はちゃんと人を理解して、寄り添ってくれる。
